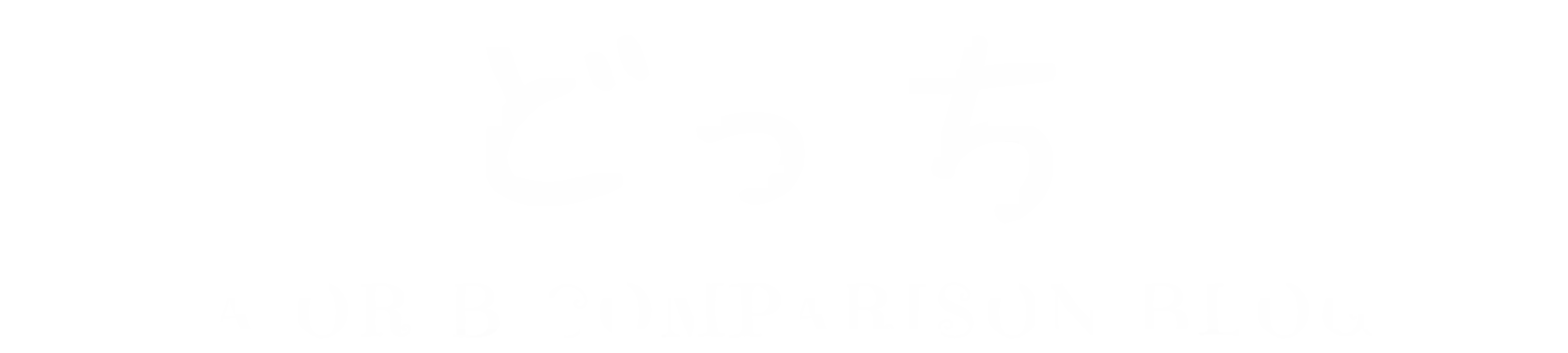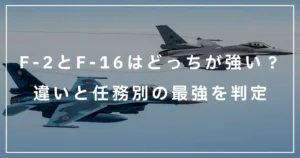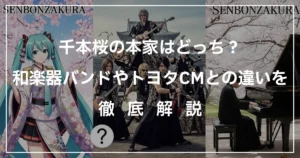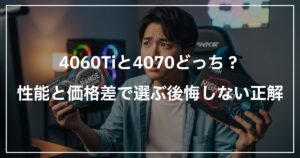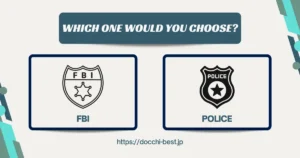簿記の資格を取得しようと考えたとき、全商簿記と日商簿記のどちらを選ぶべきか迷う人も多いでしょう。
特に、試験の難易度や合格率の違いが気になるところです。
全商簿記は商業高校生向けの資格であり、授業内容と連動しているため比較的取り組みやすい資格です。
一方、日商簿記は社会人や大学生も受験し、実務に直結した知識が求められるため、級が上がるほど難易度が高くなります。
また、独学ではなく講座を利用して学習を進める場合、通信講座と通学講座のどちらが適しているかも重要なポイントとなります。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合った学習方法を選ぶことが合格への近道となるでしょう。
この記事では、全商簿記と日商簿記の違いや試験の難易度、合格率を詳しく解説し、さらに効果的な学習方法についても紹介していきます。
簿記1級を取得して税理士試験にも合格している管理人が、最適な選択ができるような情報を提供するので、ぜひ最後まで読んでください。
- 全商簿記と日商簿記の違いや特徴を解説
- 各級の難易度や合格率の差を知れる
- 資格の評価や活用方法を把握できる
- 通信講座と通学講座の違いを学べる
- 全商簿記と日商簿記の違いや特徴を解説
- 各級の難易度や合格率の差を知れる
- 資格の評価や活用方法を把握できる
- 通信講座と通学講座の違いを学べる
全商簿記と日商簿記はどっちが難しい?等級ごとに徹底解説

上のリストから興味のある見出しに直接飛びます。
全商簿記と日商簿記の違いとは?
全商簿記と日商簿記は、いずれも簿記の知識を証明する資格ですが、主に対象者や試験の目的が異なります。
全商簿記とは?
全商簿記は正式名称を「全国商業高等学校協会主催簿記実務検定試験」といい、高校生を主な対象とした資格です。
商業高校での学習内容と連動しており、実務的な内容が多いことが特徴です。試験は3級から1級まであり、1級には会計と原価計算の2科目があります。
日商簿記とは?
一方、日商簿記(日本商工会議所主催簿記検定)は、社会人や大学生を含めた幅広い層を対象とした資格です。
経理・会計の基本的な知識から高度な財務管理までカバーしており、実際のビジネスの現場で活かせる知識が求められます。
3級は基礎レベル、2級は実務レベル、1級は高度な会計・税務の知識が必要とされます。
全商簿記と日商簿記の難易度
また、試験の難易度にも差があります。
全商簿記は学習範囲が高校の授業内容に沿っているため、商業高校の生徒には取り組みやすいですが、日商簿記は実務向けの内容が多く、特に2級以上は難易度が高めです。
したがって、取得目的や自身のキャリアに応じて、どちらを受験するかを選ぶとよいでしょう。
全商簿記の正式名称と概要
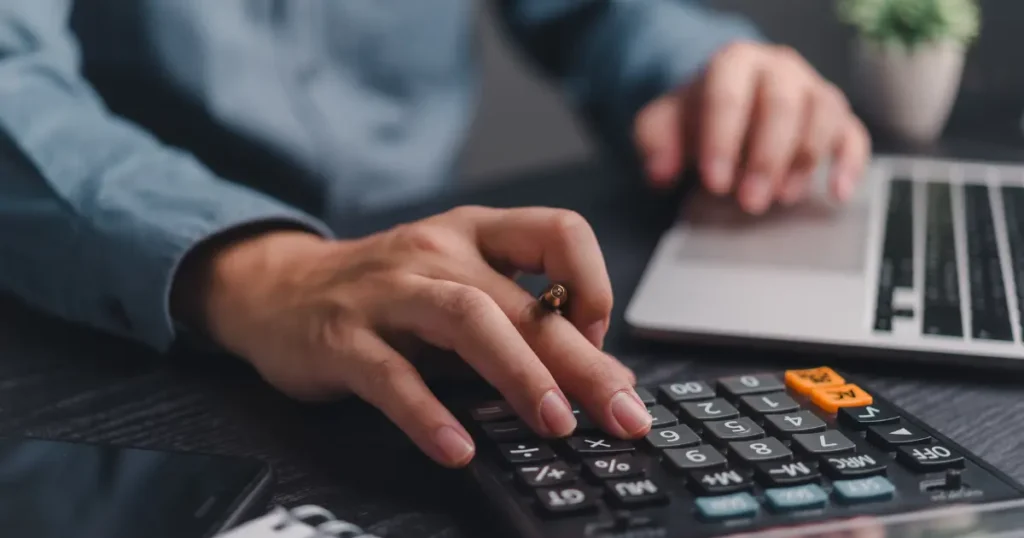
全商簿記の正式名称は「全国商業高等学校協会主催簿記実務検定試験」です。これは、全国商業高等学校協会(全商)が実施する検定試験の一つで、主に商業高校の生徒を対象としています。
全商簿記の概要
試験は1級から3級まであり、商業高校のカリキュラムと連動している点が特徴です。特に1級では「会計」と「原価計算」の2科目があり、それぞれ合格することで1級の資格が取得できます。
全商簿記の試験内容は、基礎的な帳簿の付け方から決算処理、財務諸表の作成まで幅広く、実務的な知識が問われます。
全商簿記の資格取得は意味ある?
全商簿記の資格は、商業高校生にとっては就職や推薦入試の際に評価されることが多く、一定のメリットがあります。
ただし、一般の企業では日商簿記と比べて認知度が低いため、社会人になってから経理職を目指す場合は、日商簿記の取得を検討するほうがよいでしょう。
全商簿記1級から3級の取得メリット

全商簿記3級とは?取得のメリット
全商簿記3級は、全国商業高等学校協会(全商)が実施する簿記実務検定の最も基本的な資格です。
3級の試験の内容は?
主に商業高校の生徒を対象としており、簿記の基礎を学ぶための入門レベルの試験となっています。
試験では、仕訳や帳簿記入、試算表の作成などが問われ、簿記の基本的なルールを理解することが求められます。
この資格を取得することで、企業の会計業務の流れを理解し、経理の基本スキルを身につけることができます。
3級を取得するメリットは?
商業高校の生徒にとっては、就職活動や進学の際に一定の評価を得られる点がメリットです。
また、全商簿記2級や1級へのステップアップにもつながり、将来的により専門的な簿記の知識を身につける基礎となります。
初めて簿記を学ぶ人にとっては、実務に活かせる知識を得る第一歩となる資格です。
全商簿記2級とは?取得のメリット
全商簿記2級は、全商簿記3級よりも難易度が高く、より実践的な簿記の知識が求められる資格です。
2級の試験の内容は?
2級の試験では、仕訳・転記・試算表作成だけでなく、決算処理や財務諸表の作成など、企業の会計業務に必要な内容が含まれています。
商業簿記を中心に出題され、経理業務の基礎がしっかりと身につく構成となっています。
2級を取得するメリットは?
この資格を取得することで、基本的な経理業務をこなす力が身につきます。
商業高校生にとっては、就職活動や推薦入試の際に有利になるほか、企業の事務職や経理職を目指す際にも役立ちます。
また、全商簿記1級や日商簿記2級へ挑戦する際の基礎知識としても重要です。
実務で活かせるスキルを身につけたい人や、経理分野への就職を考えている人にとって、有益な資格となります。
全商簿記1級とは?取得のメリット
全商簿記1級は、全商簿記試験の中で最も難易度が高く、商業高校生にとって最終的な目標となる資格です。
1級の試験の内容は?
試験は「会計」と「原価計算」の2科目に分かれており、両方に合格することで1級の資格が得られます。
試験内容はより実践的で、決算整理や原価計算、財務諸表の分析など、企業の経理業務で求められる知識が問われます。
1級を取得するメリットは?
この資格を取得することで、簿記の専門知識があることを証明でき、商業高校生の就職活動で強みになります。
特に、事務職や経理職を希望する場合、基本的な簿記スキルを持っていることが評価されるでしょう。
ただし、社会人になってから経理職を目指す場合は、日商簿記のほうが企業での認知度が高いため、全商簿記1級取得後に日商簿記2級や1級に挑戦するのが理想的です。
商業高校生にとっては、実務的な知識を得るだけでなく、進学や就職の際に有利になる資格といえます。
日商簿記1級から3級の取得メリット
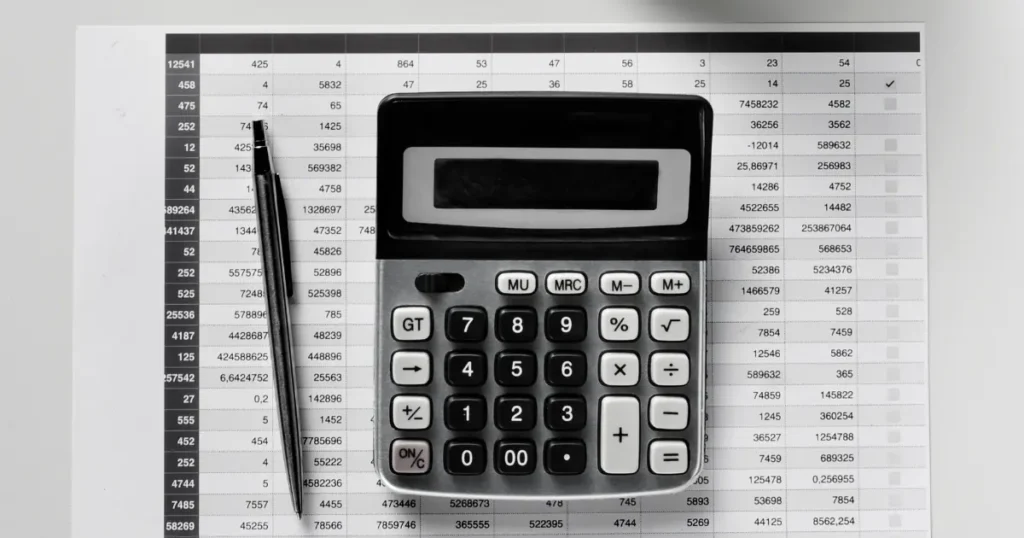
日商簿記3級とは?取得のメリット
日商簿記3級は、日本商工会議所が主催する簿記検定の中で最も基本的な資格です。
主に個人商店や中小企業の経理業務に必要な基礎知識を習得できるレベルとされており、簿記初心者でも比較的挑戦しやすい資格です。
日商簿記3級でどこまで学べる?
日商簿記3級の資格を取得することで、仕訳の基本や帳簿の記入、決算書の作成方法を学べます。
そのため、事務職や経理職を希望する人にとっては、入門資格として最適です。また、会計の基本的な知識が身につくため、経営者やフリーランスの人にも役立ちます。
 なお
なお経営者は数字を読み解かないとダメですからね
日商簿記3級取得のメリットは?
さらに、日商簿記3級は履歴書にも記載できる資格であり、経理・事務職の採用時に一定の評価を得られることもあります。
特に、未経験から経理の仕事に挑戦したい人にとっては、知識を証明する手段となるでしょう。ただし、3級は基礎レベルのため、実務で活かすには2級以上の取得を目指すのが望ましいです。
日商簿記2級とは?取得のメリット
3級では基本的な帳簿の記入や仕訳を学びますが、2級では中小企業や大企業の経理業務で必要とされる商業簿記と工業簿記を習得します。
財務諸表の作成や原価計算など、より実務的な内容が試験範囲に含まれるため、経理職を目指す人にとって重要な資格です。



というかマストな資格ですね
日商簿記2級取得のメリット
この資格を取得することで、就職や転職で有利になるメリットがあります。特に、経理・財務部門では2級を評価する企業が多く、採用時の基準となることもあります。
また、税理士試験や公認会計士試験の基礎知識としても活用できるため、キャリアアップを考えている人にもおすすめです。
さらに、経理職以外でも、会計知識があることで経営分析やコスト管理に役立ち、業務の幅を広げることができます。
日商簿記1級とは?取得のメリット
日商簿記1級は、日本商工会議所が主催する簿記検定の中で最も難易度が高い資格です。
試験範囲は商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算の4科目に及び、財務諸表の分析や税務・管理会計の知識も求められます。
合格率は10%未満と低く、独学での合格は難しいため、通信講座や専門学校を活用する人も多いです。



私は大原とTACの両方で受講し2回目で合格しました
日商簿記1級取得のメリット
この資格を取得すると、企業の経理・財務部門で即戦力として評価されやすくなります。
特に、大手企業や上場企業の経理職では高く評価され、税理士や公認会計士の受験資格も得られるため、さらなるキャリアアップにもつながります。
また、会計事務所やコンサルティング業界でも重宝されるため、専門性を高めたい人にとって大きなメリットがあります。



経理・会計の分野で長く活躍したい人にとって、取得を目指す価値のある資格です。
通信講座と通学講座、どっちがいい?


簿記資格を目指す際、通信講座と通学講座のどちらを選ぶべきかは、学習スタイルやライフスタイルによって異なります。
通信講座のメリット
通信講座のメリットは、自分のペースで学習できることです。仕事や学校と両立しやすく、通学の時間を節約できる点も魅力です。
また、講義動画を繰り返し視聴できる講座も多く、理解を深めるのに役立ちます。
一方で、学習の進捗管理は自己責任となるため、計画的に勉強できる人向けの学習方法です。
通学講座のメリット
通学講座のメリットは、講師から直接指導を受けられることです。質問がしやすく、わからない点をその場で解決できるため、特に初心者には適しています。
また、クラスメイトと学習を進めることで、モチベーションを維持しやすい点も強みです。
ただし、通学時間の確保が必要なことや、通信講座と比べて費用が高くなりがちな点がデメリットです。
おすすめの通信講座を紹介


簿記の資格取得を目指す際、通信講座は自分のペースで学習できる点が魅力です。
特に、動画講義やテキストが充実している講座を選ぶことで、効率的に学習を進めることができます。
フォーサイト
フォーサイトの簿記講座は、フルカラーのテキストと講義動画のわかりやすさが特徴です。
eラーニングシステム「ManaBun」では、スマホやタブレットでも学習が可能で、スキマ時間を有効活用できます。
初学者でも理解しやすい内容のため、独学に不安がある人におすすめです。
クレアール
クレアールは、「非常識合格法」と呼ばれる効率的な学習メソッドを採用しています。
試験で問われる重要なポイントを重点的に学べるため、短期間で合格を目指せます。
特に、日商簿記2級・1級を狙う人に適しています。
スタディング
スタディングの特徴は、完全オンラインで学習できることです。
動画講義とAIを活用した学習システムにより、短時間でも効率よく知識を身につけられます。
低コストで学べる点もメリットです。
おすすめの通学講座を紹介
通学講座は、講師から直接指導を受けられる点が大きなメリットです。
疑問をその場で解決できるため、特に初めて簿記を学ぶ人や、独学に不安がある人に向いています。
大原簿記学校
大原は、簿記資格の指導実績が豊富な専門学校です。模擬試験や過去問演習が充実しており、試験本番を意識した学習ができます。
特に、日商簿記1級や税理士試験を目指す人におすすめです。
TAC
TACは、理論と実践をバランスよく学べる講座が特徴です。講義はわかりやすく、疑問点を講師に直接質問できる環境が整っています。
また、通学しながらオンライン講義も併用できる「Wセミナー」も利用可能です。
資格の学校LEC
LECは、短期集中型のカリキュラムが魅力です。短期間で合格を目指す人向けの講座が充実しており、社会人や学生でも効率よく学べます。
また、夜間や週末のクラスもあり、仕事と両立しやすい点もメリットです。
全商簿記と日商簿記どっちが難しい?難易度や合格率を比較


上のリストから興味のある見出しに直接飛びます。
全商簿記1級と日商簿記1級の難易度比較
全商簿記1級と日商簿記1級は、同じ「1級」ですが、試験の難易度には大きな違いがあります。
全商簿記1級の難易度
全商簿記1級は、商業高校生向けの資格であり、試験範囲は高校の授業内容に準拠。試験は「会計」と「原価計算」の2科目があり、どちらにも合格することで1級の資格が得られます。
計算問題が中心で、実務に直結する知識が多く求められますが、高校生が学習しやすい内容になっているのが特徴。
合格率も比較的高く、年度によりますが20~40%程度と高めです。
日商簿記1級の難易度
一方、日商簿記1級は、簿記資格の中でも最難関とされ、合格率は10%未満と非常に低いです。試験範囲は企業会計や税務会計、管理会計まで広がり、計算問題だけでなく理論問題も含まれます。
さらに、公認会計士試験や税理士試験の基礎となる知識が問われるため、独学での合格は困難とされています。
このように、全商簿記1級は高校生向けの実務的な資格で、比較的取得しやすいのに対し、日商簿記1級は社会人でも合格が難しい高度な資格です。
就職や転職で評価されやすいのは日商簿記1級ですが、全商簿記1級は高校生にとっては有利な資格の一つと言えるでしょう。
全商簿記1級と全商簿記2級の違い


全商簿記1級と2級は、試験範囲や難易度に違いがあります。
全商簿記2級とは?
全商簿記2級では、主に商業簿記を学び、仕訳や決算書の作成などの基本的な経理業務が理解できるようになります。
試験では、仕訳処理や勘定記入、決算整理などが出題され、日々の取引を帳簿に記録する力が求められます。
合格率は年度によりますが、40~50%程度と比較的高めです。
全商簿記1級とは?
一方、全商簿記1級では、商業簿記に加え、工業簿記の知識が求められます。特に、原価計算の分野が加わることで、製造業における会計処理も学ぶことができます。
また、1級では「会計」と「原価計算」の2科目に合格しなければならず、2級よりも出題範囲が広くなります。
合格率は2級より低く、20~40%程度です。
このように、全商簿記2級は主に商業簿記の基礎を学ぶレベルですが、1級になると原価計算や高度な会計処理も含まれるため、より専門的な知識が求められます。
そのため、1級を目指す場合は、2級の内容をしっかりと理解しておくことが重要です。
簿記1級の合格者数は日本で何人?


簿記1級の合格者数は、毎年限られた人数にとどまります。特に日商簿記1級の合格率は10%未満と低いため、合格者はそれほど多くありません。
日商簿記1級の年間合格者数
日本商工会議所が発表するデータによると、日商簿記1級の合格者数は年間で約1,000~2,000人程度です。
これは、年間数万人が受験する中での数字であり、いかに難関資格であるかがわかります。
試験は年に2~3回実施されますが、そのたびに合格者数は少なく、難易度の高さを物語っています。
全商簿記1級の年間合格者数
一方、全商簿記1級の合格者は日商簿記1級よりも多く、年度によりますが毎年1万人以上が合格しています。
商業高校生が中心の資格であり、日商簿記1級と比べて取得しやすいため、合格者数も多くなります。
このように、簿記1級の合格者数は資格の種類によって大きく異なります。特に日商簿記1級は非常に狭き門であり、取得できれば会計や経理の専門知識を持つ証明として高く評価されるでしょう。
全商簿記1級は意味ない?評価と活用法
「全商簿記1級は意味がないのでは?」と考える人もいるかもしれませんが、これは取得する目的によって評価が異なります。
商業高校生には価値あり
まず、全商簿記1級は商業高校生向けの資格であり、就職時にアピールできる点が大きなメリットです。
特に、経理職や事務職を希望する場合、簿記の知識を持っていることが評価され、企業によっては採用時にプラス要素となることもあります。
また、学校推薦での進学や就職活動に有利に働くケースもあるため、商業高校生にとっては価値のある資格です。
社会人や転職市場では価値なし
一方で、社会人や一般の求職者が経理職を目指す場合、企業が評価するのは日商簿記であることが多いため、全商簿記1級の知名度はやや低くなります。
そのため、転職市場ではあまり活用しにくい資格と考えられがちです。ただし、全商簿記1級を取得した後に日商簿記2級や1級に挑戦することで、より強いスキルを証明することができます。
つまり、全商簿記1級は商業高校生にとっては有益な資格ですが、社会人が経理職を目指す場合は、日商簿記の取得を優先した方が良いでしょう。
全商簿記1級の次は何を取得すべき?


全商簿記1級を取得した後、次にどの資格を目指すべきかは、進路や目的によって異なります。
経理や会計の分野で活かしたい場合、より実務向けの資格に挑戦するのがおすすめです。
王道は日商簿記2級や1級
最も一般的な選択肢は、日商簿記2級や1級の取得です。日商簿記は企業での評価が高く、特に2級は経理職を目指す際の基礎資格として知られています。
全商簿記1級を取得した人であれば、日商簿記2級の範囲と一部重なるため、比較的スムーズに学習を進められるでしょう。
税理士や公認会計士
また、税理士や公認会計士などの国家資格に挑戦する道もあります。これらの資格は非常に難易度が高いですが、会計分野での専門性を高め、将来的に独立や高収入を目指すことも可能です。
一方、経理以外の事務職を目指す場合は、MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)やFP(ファイナンシャルプランナー)の資格を取得するのも有効です。
これらは実務での活用範囲が広く、企業での評価も高いため、スキルの幅を広げることができます。
全商簿記 日商簿記 どっちが難しい?特徴と違いを比較:総括
最後にこの記事のポイントをまとめておきます。
- 全商簿記は高校生向け、日商簿記は社会人・学生向け
- 全商簿記は学校の授業と連動、日商簿記は実務向けの内容
- 全商簿記1級は「会計」と「原価計算」の2科目に分かれる
- 日商簿記1級は税務・財務・管理会計を含み、難易度が高い
- 全商簿記1級の合格率は20~40%、日商簿記1級は10%未満
- 日商簿記は企業の評価が高く、転職や就職に有利
- 全商簿記1級は商業高校生の進学や就職で活用される
- 全商簿記2級の合格率は約40~50%で比較的取得しやすい
- 全商簿記1級取得後は日商簿記2級・1級へのステップアップが推奨される
- 簿記1級の年間合格者数は日商簿記が約1,000~2,000人と少ない
- 全商簿記1級は計算問題が中心、日商簿記1級は理論問題も多い
- 日商簿記3級は基礎レベルで、経理・事務職の入門資格として最適
- 通信講座は自分のペースで学習できるが、自己管理が必要
- 通学講座は講師に直接質問でき、初心者に向いている
- 資格の活用方法は、目的やキャリアに応じて選ぶことが重要